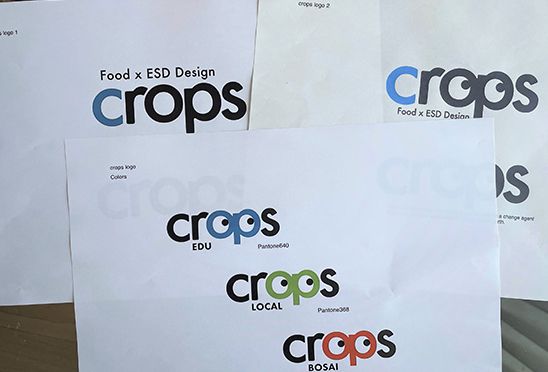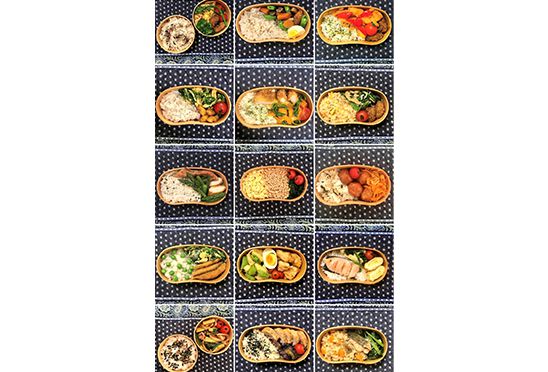OB/OGのご紹介

【11期】2019年度春修士課程修了
須賀 智子
すが ともこ
外資系広告会社でのマーケティング・メディアプランニング業務に10数年従事した後、食を専門とするメディア・料理通信社へ。同社のWeb事業とSDGs事業の立ち上げと推進を担う。主に「食で未来をつくる・食の未来を考える」をスローガンに、食の生産から消費に至る様々なフェーズでの課題解決に向けた取材活動と情報発信、 “食×SDGs”をテーマにしたカンファレンスの企画運営等を行う。2021年9月、修士研究から着想し、食を通じたESD(持続可能な開発のための教育)推進のための新たな事業を立ち上げる。
研究タイトル
中学校でのESD導入のための食を活用したカリキュラム・デザイン手法の設計と評価
Design and Evaluation of Curriculum Design Method with Food Perspectives for Adapting Education for Sustainable Development in Junior High Schools
研究の概要
学校教育の現場でESD(持続可能な開発のための教育)を基盤とした「持続可能な社会の創り手」の育成が求められているなか、適切なカリキュラムの欠如や、コマ数・人材といったリソースの制約等の要因から十分に実践されていないことが問題となっている。本研究では中学校でのESD導入を促進させることを目的に、実践主体である教員が連携してESDに取り組むための、食をテーマに教科横断するカリキュラムデザイン手法を提案し、その有用性を評価した。
SDM的ポイント
本研究では、歴史や地理、生物といった複数教科をまたいで扱うことができる「食」を題材に、事象の背景・成り立ちを体系的多面的に捉える力や、環境や多様性を尊重する価値観を養うためのアプローチを提案した。これは、学問分野横断的、モノゴトをシステムとしてとらえた全体俯瞰的な問題解決に関する研究機関であり、関係者が互いに協力し、ビジョンを共有し多様なアプローチを考えていくSDM的な眼差しと重なる点だと考えている。
この研究への神武先生のコメント
「食に関する社会課題に関する研究を俯瞰的に実施したいんです。」という相談を頂いた入学前から修了されるまで、そのアプローチや思考の観点の変化や拡がっていったものの、研究で取り組みたいことの軸がブレずに進められたからこそ、修士研究の成果とそれを経ての起業にまで繋がったのだと感じている。修士研究では、中学校でのESD教育導入のためのひとつの提案として、教科横断型の教育テーマとして「食」を扱い、システムデザイン・マネジメントの考え方を取り入れたカリキュラムデザイン手法を設計し、その有効性を実際の中学校との連携によって示した。その成果は、その後のお仕事、また、起業にもつながっており、研究室としても今も連携を続けている。
慶應SDMで学んだことが
今の自分にどう役立っているか
食を取り巻く社会・環境問題解決の一翼を担うために必要な学びを、とSDMを志望したが、WHY?に真摯に向き合う態度や全体俯瞰力を身に着けていく過程で、「食」に関して、様々な問題を内包しつつも同時に解決策を導き出せる新たな可能性を見出せたことは、仕事に大きく役立っている。
また研究対象とする「システム」が学生それぞれに異なる中で議論や対話を重ねられたことは、狭い視野を多少なりとも広げていくことにつながり、多様な視点を大切にしたいという思いをいつも携えることができるようになった。
ちなみに、神武研での「研究実施の過程でかならず考えるべきことリスト」は、仕事上で(HOWに注力しがちな)企画を立案するとき、様々な議題で娘と対話するとき、自分自身の行動を内省するとき…と、思考を整理整頓する様々な場面で活かせるので、ずっと壁に貼り続けている。
近況報告